質問4 医療費が高額になったときは?
同じ月内に支払われる医療費には、上限額が決められています。上限額を超えてお支払いされた分は、高額療養費として支給されます。
上限額は以下の「高額医療費の対象となる自己負担限度額(月額)」の項目にある表組をご参照ください。
また、入院された時の医療費の支払額(ひと月分)も下表の自己負担限度額が上限となります。ただし、食費や差額ベッド代などは含まれませんのでご注意ください。
高額療養費の支給の流れ
- 市役所へ支給申請書をご提出ください。(申請書様式は以下のファイルをご覧ください。)(新しいウィンドウが開きます)
- 医療機関を受診されると、その内容が広域連合へ提出されます。
- 医療機関の報告に基づいて、広域連合では自動的に高額療養費の計算をします。
- 高額療養費が発生したときには、広域連合よりお届け口座に振り込まれます。
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 108.0KB)
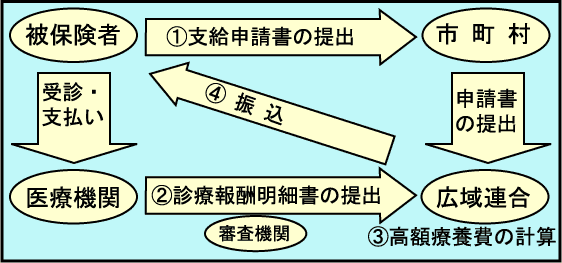
高額医療費の対象となる自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 窓口負担 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3
(住民税課税所得690万円以上) |
3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注1) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注1) | ||||
|
現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上) |
3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注2) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注2) | ||||
|
現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上) |
3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注3) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注3) | ||||
|
一般2 |
2割 |
18,000円または【6,000円+(総医療費-30,000円)×10%(令和7年9月まで)】の低い方を適用 | 57,600円(注4) | ||||
|
一般1 (住民税課税所得145万円未満等) |
1割 | 18,000円 | 57,600円(注4) | ||||
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 | |||
| 低所得者1 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | ||||
(注釈1)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
(注釈2)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
(注釈3)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
(注釈4)過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
- 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の人。
(詳しくは、以下のリンク「質問3 窓口で支払う医療費の負担割合は?」をご覧下さい。) - 一般2:同一世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいる世帯で、下記⓵または⓶に該当する人がいる世帯の人。
⓵同一世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
⓶同一世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 - 一般1:「現役並み所得者」「一般2」「低所得者2」「低所得者1」以外の人。
- 低所得者2:世帯員全員が住民税非課税である人。
- 低所得者1:世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の人。
所得区分を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。
住民税非課税世帯(低所得者1・2)の人または、現役並み所得者1・2の人は病院での窓口負担が自己負担限度額までとなる「資格確認書」を交付できますので、ご申請ください。
- 高額療養費が発生した場合の振り込みは、通常、受診された月の約3ヵ月後となります。振り込みの前には広域連合から支給通知書(ハガキ)が送付されますので、ご確認ください。
- 高額療養費の振り込みが遅れることがあります。
高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書に基づき、広域連合で計算されます。診療報酬明細書の内容に不備がある場合は、医療機関に返戻されますので、振り込みが遅れる場合があります。
入院時の食事代がかかったとき(入院時食事療養費)
入院したときは、下の表のとおり食事の標準負担額を自己負担します。
食事代は、高額療養費の計算には含まれませんので、ご注意ください。
| 所得区分 | 1食あたり | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 510円(注釈1) | |
| 一般1・2 | 510円(注釈1) | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2(90日までの入院) | 240円 |
| 低所得者2(過去12ヵ月で90日を超える入院) | 190円(注釈2) | |
| 低所得者1 | 110円 | |
(注釈1)一部300円の場合があります。
(注釈2)適用を受けるためには、市役所で申請が必要となります。
- 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の人。
(詳しくは、以下のリンク「質問3 窓口で支払う医療費の負担割合は?」をご覧下さい。) - 一般2:同一世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいる世帯で、下記⓵または⓶に該当する人がいる世帯の人。
⓵同一世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
⓶同一世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 - 一般1:「現役並み所得者」「一般2」「低所得者2」「低所得者1」以外の人。
- 低所得者2:世帯員全員が住民税非課税である人。
- 低所得者1:世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の人。
所得区分を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。
住民税非課税世帯(低所得者1・2)の人または、現役並み所得者1・2の人は、病院での窓口負担が自己負担限度額までとなる「資格確認書」を交付できますので、ご申請ください。
なお、低所得者1・2の人で限度区分が記載された証を掲示する前に支払いをした場合、食事代は1食510円で計算されます。食事代は原則、遡及して申請することはできませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
被保険者証または資格確認書、領収書、振込先が確認できるもの、個人番号のわかるもの
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両方を利用する人に、負担がかかりすぎないように、合計額の年間限度額が決められました。
1年間(8月~翌年7月まで)にかかった医療費と介護サービス利用料の合計額が高額になった場合、下表の限度額を超えた分が払い戻されます。
払い戻しを受けるためには、申請が必要になります。
| 所得区分 | 後期高齢者医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 | |
| 現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
| 現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
| 一般1・2 | 56万円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 | |
- 食事や居住費、差額ベッド代などは合算の対象にはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 医療係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線328)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2024年06月01日