水質基準項目の説明
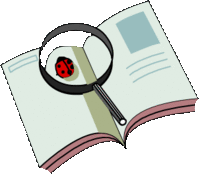
水道水には、全ての水道が守るべき水質基準として、「健康に関する項目」と「水道水が有すべき性状に関する項目」が定められています。
「健康に関する項目」(31項目)
生涯にわたって連続的に水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにして、さらに安全率を加味して設定したものです。(表中の1~31項目)
「水道水が有すべき性状に関する項目」(20項目)
水道水を生活用水にするのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずる恐れのない水準として設定したものです。(表中の32~51項目)
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1.一般細菌 | 1ミリリットルあたり100個以下 | 病原生物 | 高濃度有機栄養物の寒天培地中で、人の体温環境下で1日培養したとき、検出される全ての細菌をいう。塩素殺菌した水道水には検出されにくいが、大量に検出した場合は病原生物等汚染の疑いがあることになる。 |
| 2.大腸菌 | 検出されないこと | 病原生物 | 人や動物の腸管内や土壌に多く存在する。塩素殺菌した水道水には検出されないが、検出した場合は病原生物等汚染の疑いがあることになる。クリプトスポリジウムの指標検査としても活用している。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 3.カドミウム(Cd)及びその化合物 | 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 | 重金属 | 鉱山排水や工場排水等により検出されることがある。カドミウムは蓄積性があり、過剰摂取による中毒症状に骨や腎臓障害等がある。イタイイタイ病の原因物質として知られている。 |
| 4.水銀(Hg)及びその化合物 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 | 重金属 | 地質由来及び鉱山排水や工場排水等により検出されることがある。水銀は蓄積性があり、中毒症状に中枢神経系統の障害がある。特に有機水銀(メチル水銀)は水俣病の原因物質として知られている。 |
| 5.セレン(Se)及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 重金属 | 鉱山排水や工場排水等により検出されることがある。セレンは生体微量必須元素の一つであるが、過剰摂取による中毒症状に貧血や胃腸障害及び肝機能障害等がある。 |
| 6.鉛(Pb)及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 重金属 | 鉱山排水や工場排水及び鉛管からの溶出により検出されることがある。鉛は蓄積性があり、過剰摂取による中毒症状に神経系統障害や造血機能障害等がある。 |
| 7.ヒ素(As)及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 重金属 | 地質由来及び鉱山排水や工場排水等により検出されことがある。砒素は蓄積性があり、過剰摂取による中毒症状に粘膜炎症や皮膚障害(黒色色素沈着、硬化、脱毛等)がある。 |
| 8.六価クロム(Cr6+)化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 重金属 | 六価クロムは自然界ではほとんど存在せず、鉱山排水や工場排水によって検出されることがある。クロムは生体微量必須元素の一つであるが、過剰摂取すると細胞障害により染色体異常を引き起こすと言われている。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 9.亜硝酸態窒素(NO2) | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 無機物質 | 水中に含まれる亜硝酸イオンの窒素量をいう。 |
| 10.硝酸態窒素(NO3)及び亜硝酸態窒素(NO2) | 1リットルあたり10ミリグラム以下 | 無機物質 | 水中に含まれる硝酸イオン及び亜硝酸イオンの窒素の合計量をいう。農業排水や工場排水等により高濃度に検出されることがある。過剰摂取した乳児はブルーベビー病(チアノーゼ症)にかかることがある。 |
| 11.フッ素(F-)及びその化合物 | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 | 無機物質 | 地質由来及び工場排水等により検出されることがある。適量摂取のフッ素は虫歯の予防効果があるが、過剰摂取すると斑状歯になることがある。地域によっては大量に検出されることがあり、除去が難しい。 |
| 12.ホウ素(B)及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 無機物質 | 地質由来及び工場排水等により検出されることがある。海水製造の飲料水に含まれることが多い。過剰摂取すると雄生殖器官に影響を及ぼすといわれている。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 13.四塩化炭素(CCl4) | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 | 左記8項目は揮発性有機化学物質に属し、第1種及び第2種有機溶剤等に指定されている。ドライクリーニングや金属洗浄剤等に使用されており、地下浸透しやすく地下水汚染物質として知られている。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると神経系や肝・腎機能系の障害を生ずるといわれている。 |
| 14. 1.4-ジオキサン(C4H8O2) | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 | 左記8項目は揮発性有機化学物質に属し、第1種及び第2種有機溶剤等に指定されている。ドライクリーニングや金属洗浄剤等に使用されており、地下浸透しやすく地下水汚染物質として知られている。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると神経系や肝・腎機能系の障害を生ずるといわれている。 |
| 15.シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2ジクロロエチレン (CHCl=CHCl) |
1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 | 左記8項目は揮発性有機化学物質に属し、第1種及び第2種有機溶剤等に指定されている。ドライクリーニングや金属洗浄剤等に使用されており、地下浸透しやすく地下水汚染物質として知られている。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると神経系や肝・腎機能系の障害を生ずるといわれている。 |
| 16.ジクロロメタン(CH2Cl2) | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 | 左記8項目は揮発性有機化学物質に属し、第1種及び第2種有機溶剤等に指定されている。ドライクリーニングや金属洗浄剤等に使用されており、地下浸透しやすく地下水汚染物質として知られている。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると神経系や肝・腎機能系の障害を生ずるといわれている。 |
| 17.テトラクロロエチレン (CCl2=CCl2) |
1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 | 左記8項目は揮発性有機化学物質に属し、第1種及び第2種有機溶剤等に指定されている。ドライクリーニングや金属洗浄剤等に使用されており、地下浸透しやすく地下水汚染物質として知られている。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると神経系や肝・腎機能系の障害を生ずるといわれている。 |
| 18.トリクロロエチレン (CHCl=CCl2) |
1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 | 左記8項目は揮発性有機化学物質に属し、第1種及び第2種有機溶剤等に指定されている。ドライクリーニングや金属洗浄剤等に使用されており、地下浸透しやすく地下水汚染物質として知られている。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると神経系や肝・腎機能系の障害を生ずるといわれている。 |
| 19.ベンゼン(C6H6) | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 | 左記8項目は揮発性有機化学物質に属し、第1種及び第2種有機溶剤等に指定されている。ドライクリーニングや金属洗浄剤等に使用されており、地下浸透しやすく地下水汚染物質として知られている。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると神経系や肝・腎機能系の障害を生ずるといわれている。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 20.シアン化物イオン 及び塩化シアン |
1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | シアン化物イオンは工場排水等により検出されることがあり、塩化シアンは浄水過程の塩素処理で生成されることがある。過剰摂取するとチアノーゼ症状(唇が紫色になる)になることがある。 |
| 21.塩素酸(ClO3) | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 塩素酸は浄水過程における塩素殺菌剤の次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)溶液に含まれる。赤血球への障害作用があるといわれている。 |
| 22.クロロ酢酸(CH2ClCOOH) | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 原水中に含まれる酢酸(CH3COOH)等が浄水過程の塩素処理で生成したもので、発ガン性物質の可能性がある。酢酸は食酢の主成分であり、家庭排水及びゴミ焼却からの影響が大きく河川水取水では注意を要する。 |
| 23.ジクロロ酢酸(CHCl2COOH) | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 原水中に含まれる酢酸(CH3COOH)等が浄水過程の塩素処理で生成したもので、発ガン性物質の可能性がある。酢酸は食酢の主成分であり、家庭排水及びゴミ焼却からの影響が大きく河川水取水では注意を要する。 |
| 24.トリクロロ酢酸 (CCl3COOH) |
1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 原水中に含まれる酢酸(CH3COOH)等が浄水過程の塩素処理で生成したもので、発ガン性物質の可能性がある。酢酸は食酢の主成分であり、家庭排水及びゴミ焼却からの影響が大きく河川水取水では注意を要する。 |
| 25.総トリハロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 総トリハロメタンはクロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムの4物質の総計をいう。原水中に含まれるメタン(CH4)等の有機物質が浄水過程の塩素処理でハロゲン化(塩素化・臭素化)したもので、発ガン性物質の可能性がある。 |
| 26.クロロホルム(CHCl3) | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 総トリハロメタンはクロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムの4物質の総計をいう。原水中に含まれるメタン(CH4)等の有機物質が浄水過程の塩素処理でハロゲン化(塩素化・臭素化)したもので、発ガン性物質の可能性がある。 |
| 27.ジブロモクロロメタン (CHClBr2) |
1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 総トリハロメタンはクロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムの4物質の総計をいう。原水中に含まれるメタン(CH4)等の有機物質が浄水過程の塩素処理でハロゲン化(塩素化・臭素化)したもので、発ガン性物質の可能性がある。 |
| 28.ブロモジクロロメタン (CHCl2Br) |
1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 総トリハロメタンはクロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムの4物質の総計をいう。原水中に含まれるメタン(CH4)等の有機物質が浄水過程の塩素処理でハロゲン化(塩素化・臭素化)したもので、発ガン性物質の可能性がある。 |
| 29.ブロモホルム(CHBr3) | 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 総トリハロメタンはクロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムの4物質の総計をいう。原水中に含まれるメタン(CH4)等の有機物質が浄水過程の塩素処理でハロゲン化(塩素化・臭素化)したもので、発ガン性物質の可能性がある。 |
| 30.臭素酸(HBrO3) | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 臭素酸は、浄水過程で使う消毒剤である次亜塩素酸ナトリウム溶液内に含まれている。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると中枢神経系及び腎機能に障害が生ずるといわれている。 |
| 31.ホルムアルデヒド (HCHO) |
1リットルあたり0.08ミリグラム以下 | 消毒副生成物 | 石炭や木等を燃やした煙の中にも存在し、浄水過程の塩素処理及びオゾン処理で検出されることがある。発ガン性物質の可能性があり、過剰摂取すると胃機能及び生殖器等に障害が生ずるといわれている。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 32.亜鉛(Zn)及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 色 | 亜鉛メッキ鋼管からの溶出及び工場排水等により検出されることがある。亜鉛は生体微量必須元素の一つであるが、基準値を超えると水道水が白濁し、またお茶の味に影響することがある。 |
| 33.アルミニウム(Al) 及びその化合物 |
1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 色 | 地質由来及び工場排水等により検出されることがある。アルツハイマー病の原因物質といわれるが、明確な因果関係はない。基準値を超えると水道水が変色(白濁)することがある。 |
| 34.銅(Cu)及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 色 | 給湯器内の銅管からの溶出及び工場排水等により検出されることがある。銅は生体微量必須元素の一つであるが、基準値を超えると金属味を帯び、洗濯物等を着色(青系色)する原因となる。 |
| 35.鉄(Fe)及びその化合物 | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | 色 | 老朽化した鉄管からの溶出及び工場排水や下水排水により検出されることがある。鉄は生体微量必須元素の一つであるが、基準値を超えると洗濯物が着色(赤・黄系色)したり、金気臭による異臭味を与える。 |
| 36.マンガン(Mn) 及びその化合物 |
1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 色 | 地質由来及び工場排水等により検出されることがある。マンガンは生体微量必須元素の一つであるが、過剰摂取すると肝機能等に障害を起こすことがある。配・給水管内で酸化蓄積すると「黒い水」の原因となる。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 37.ナトリウム(Na) 及びその化合物 |
1リットルあたり200ミリグラム以下 | 味覚 | 地質由来及び家庭排水、工場排水等により多量検出されることがある。ナトリウムは生体微量必須元素の一つであるが、慢性的な過剰摂取は高血圧症等の成人病を引き起こす。 |
| 38.塩化物イオン(Cl-) | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 味覚 | 水中に溶存している塩素イオン化合物の総数をいう。地質由来及び家庭排水、工場排水等により多量検出されることがある。大量の塩素イオンは、水に味をつけるため味覚を損なうことになる。 |
| 39.総硬度(カルシウム・ マグネシウム等) |
1リットルあたり300ミリグラム以下 | 味覚 | 水中のカルシウムイオン(Ca2+)及びマグネシウムイオン(Mg2+)の総量を炭酸カルシウム(CaCO3)の量(1リットルあたりのミリグラム)に換算したもの。基準値を超えると胃腸を害して下痢等を起こし、生活的には石鹸の泡立ちが悪く洗浄効果が少なくなる。 |
| 40.蒸発残留物 | 1リットルあたり500ミリグラム以下 | 味覚 | 水を蒸発させた時に得られる残留物であって、ほとんどがCa、Mg、Si、Na、K等の鉱物でミネラル分ともいわれている。水中に不純物が混じっていると数値も増加し、味覚にも影響する。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 41.陰イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 発泡 | 水中に存在すると泡立ちの原因となるため発泡汚濁の指標となった。炊事・洗濯等の家庭排水から検出されることがあり、陰イオン界面活性剤に付随するリン酸塩は水源の富栄養化が問題視されている。 |
| 42.非イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 発泡 | 有機アルコールを原料とし、イオン性を示さない界面活性剤(洗剤)である。主に洗浄剤や乳化剤として使われるが、中には環境ホルモン物質も含まれているといわれている。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 43. 2-メチルイソボルネオール | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | 臭い | 両者ともカビ臭の原因物質であり、前者は墨汁の臭いを呈し、後者は純カビ臭を呈する。6~9月の水温上昇期に富栄養化した水域で藍藻類及びプランクトン等が発生し、両者のカビ臭物質を産生する。近年は冬期にも発生している。10ppb程度でもその臭いが感じられることがある。 |
| 44.ジェオスミン | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | 臭い | 両者ともカビ臭の原因物質であり、前者は墨汁の臭いを呈し、後者は純カビ臭を呈する。6~9月の水温上昇期に富栄養化した水域で藍藻類及びプランクトン等が発生し、両者のカビ臭物質を産生する。近年は冬期にも発生している。10ppb程度でもその臭いが感じられることがある。 |
| 45.フェノール類 (C6H5OH等) |
1リットルあたり0.005ミリグラム以下 | 臭い | 工場排水及びアスファルト舗装道路の洗浄水等により検出されることがある。フェノール類を含んだ原水を塩素消毒するとクロロフェノール等に変化し不快な臭気を与える。 |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 46.有機物 {全有機炭素(TOC)の量} |
1リットルあたり3ミリグラム以下 | 汚濁 | 水中に存在する有機物に含まれる炭素の総量をいい、有機性汚濁の指標として原水及び浄水処理過程の状況把握に役立つ。水道水源に汚水や排水等が流入すると数値が上がる |
| 項目 | 基準値 | 区分 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 47.pH値 | 5.8~8.6 | 基礎的性状 | 水の「アルカリ性」「酸性」「中性」の性質を数値(1~14)で示したもの。「中性」は7で、この7を基準に低いと「酸性」、高いと「アルカリ性」となる。基準をはみ出ると味覚等に影響を及ぼす。 |
| 48.味 | 異常でないこと | 基礎的性状 | 水の味は溶存する物質の種類及びその濃度によって味覚が影響される。また臭気との関連性があり、異臭を除去すると味も改善される。味の種類には、塩味・苦味・渋味・甘味・酸味等がある。 |
| 49.臭気 | 異常でないこと | 基礎的性状 | 水の臭気は溶存する物質の種類及びその濃度によって臭いが影響される。臭気の種類には、芳香臭・土臭・カビ臭・魚臭・薬品臭・腐敗臭等がある。井戸原水では、硫化水素臭が多い。 |
| 50.色度 | 5度以下 | 基礎的性状 | 水の色の程度を数値で表したもの。基準値である色度5度の水は、コップや洗面器に汲んでも肉眼では感じにくい。水中に含まれる鉄やマンガン等が酸化して色度が増すことがある。 |
| 51.濁度 | 2度以下 | 基礎的性状 | 水の濁りの程度を数値で表したもの。基準値である濁度2度の水は、コップや洗面器に汲んでも肉眼では感じにくい。平成8年よりクリプトスポリジウム対策として浄水場出口で0.1度以下を目標としている。 |
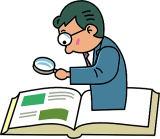
この記事に関するお問い合わせ先
業務課
郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-53-3661
ファックス:0743-52-1923
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2021年03月19日