まちかどレポート504
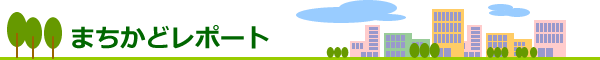
まちかどレポート504 再発見ウォーク「平端駅から新庄町一帯」
(まちかどレポーター 佐藤)
再発見ウォーク「平端駅から新庄町一帯」(平成29年12月20日掲載)
今年の再発見のテーマは、大和郡山市制60周年事業で発行された「石碑の声を聴いてみよう」の石碑を巡るウォーキング。12月6日は、平端駅から治道の新庄町まで行き、筒井駅まで歩きました。
【当日のコース】 近鉄平端駅~順慶覆堂~八条ケ渕跡~新庄町一帯の石碑~近鉄筒井駅

写真のオベリスクのような石碑は、伊豆七条町の佐保川堤防にある石碑で、「所属組換記」と彫ってあります。これは明治の初めに郡制が施行され、当時の伊豆七条村が添下郡と添上郡に分けられてしまったのを、住民たちが国に訴訟を起こして元に戻したことを伝えている碑です。
「なんで、一つの村を分けなあきまへんね?」
理由は、村の中央を南北に通る道を境に添下郡、添上郡に分かれていた時があったんです。しかしそれは、遠い遠い奈良時代で、まだ村も存在しなかった頃の話です。明治政府の官僚が、突然古代に戻してしまったんですね。
この石碑は当時の村人たちの結束を宣言するモニュメント、堤防の斜面に立てられているので、碑文を見ようとすると写真のように見上げなければならない。まるで、独立の英雄を讃える石碑のようです。

出発地の平端駅。平端は平坦地の端にあるから平端になったとか。この日は市長も来られました。

長安寺町にある順慶五輪塔覆堂、筒井順慶の墓所です。順慶の死後すぐに建立されたもので、中の五輪塔や、一周忌に建立された灯篭とともに、国の重要文化財に指定されている貴重なもの。平端駅の近くですが、このひっそりとした町のお堂が、そんなに偉いものだったとは…。まさにこれは「まちかど重要文化財」。
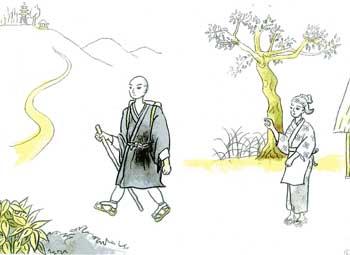
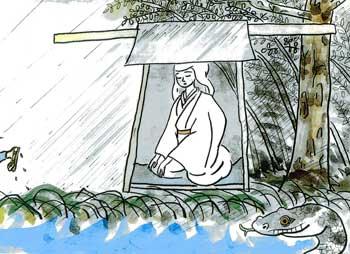


昔、八条町の北の一帯には、奈良の代表的な民話の一つ、「嫁取橋伝説」の「八条ケ渕」が広がっていた所です。この日は、ボランティアガイドさんの紙芝居があり、上の2枚はその一部を写させてもらったものです。この絵は元ガイドクラブの会員の女性の方が書かれたそうです。
今、ここには西名阪と京奈和道のジャンクションが建設されて、風景は一変されました。ただ八条ケ渕の碑だけがここが悲しい物語の舞台であったことを伝えているのです。

治道いちご。いちごは年中出荷期です。


新庄町にある石碑で、左のガイドが説明しているのは、新庄の古い土地の名を伝える「鉾立大明神」、右は今は陶製の小さな祠だけが残る「八王子神社」の石碑。


これも新庄町の石碑で、左は幕末に近いころの江戸時代の道標。「左、みわ はせ 右、よしの かうや」と刻まれています。
右の写真は蕪村の句碑で、「むし啼くや 河内通いの 小でうちん」。
蕪村はもちろん江戸時代中期の俳人。「河内通い」は平安時代の歌人・在原業平が天理の櫟本から河内高安の恋人の元に通ったという話で、伊勢物語に語られるこの話は当時の人にはよく知られた昔話だったのでしょう。
業平が櫟本から高安に通った道は「業平道」と呼ばれて、今日でも郡山から安堵、斑鳩ときれぎれに残されています。新庄町もそのルートの一部で先の道標も、業平道沿いにあるのです。
そうなんです。業平道は江戸時代から明治の人々が歩いた街道で、当時のメインルートから少し外れた道は、旅人に平安時代の旧い物語を思い出させる歴史の道だったのです。









更新日:2021年03月19日