まちかどレポート352
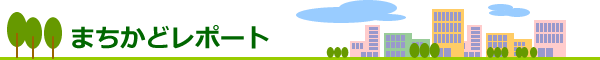
まちかどレポート352 新年は、「天馬で飛躍!」
(2013年12月20日撮影 まちかどレポーター・安江)
新年は、「天馬で飛躍!」(伝統工芸・赤膚焼)(平成25年12月27日掲載)

「三の丸歴史愛好会」で、赤膚焼窯元 小川二楽(赤膚焼研究会事務局)を見学しました。
窯元は、干支の焼き物つくりの真最中。

「新年は天馬のように飛躍する年になるよう祈っています」と作品と赤膚焼について話しを伺いました。

郡山城主となった豊臣秀吉の弟・秀長が尾張の国・常滑の陶工を招いて茶器を焼かせたのが始まりとされています。赤膚焼の由来は、焼物が赤味を帯びていたため、または窯があった五条山の別名赤膚山に由来するという両説があるようです。
江戸時代後期には、名工・奥田木白が仁清写しの技術を駆使して広く世に知らしめ、赤膚焼中興の祖と尊ばれ、小堀遠州が好んだ遠州七窯の一つにも数えられています。




ほんのりと赤い地肌に、乳白色の釉薬をかけ、奈良絵と呼ばれる絵付けを施したものがよく知られています。奈良絵は諸説があるようですが、釈迦の生涯を描いた過去現在因果経を手本にしたもので、上下2本の線の中に、人形・家・奈良の風景・鹿などの文様が描かれています。大和郡山市に窯元は2軒、奈良市に4軒ありますが、それぞれの絵の特徴は少しずつ異なるようです。
窯元を出て、矢田筋にある奥田木白の墓がある円融寺を訪ねました。

この日は冷え込みがきつく、大雪が降ってきました。瞬く間に雪が郡山の街を包み、まるで赤膚に真っ白い釉薬をかけられた器に、2014年はどのような街が描かれるのかとワクワク感が感じられるような師走の瞬間でもありました。
今年も「まちかどレポート」にアクセスいただき、ありがとうございました。
よいお年をお迎えください。









更新日:2021年03月19日