まちかどレポート236
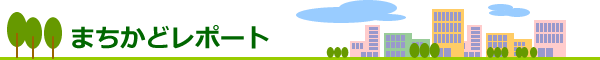
まちかどレポート236 中世石造物の研究で博士号
(2011年12月2日 取材)(まちかどレポーター フリーター・K)
山川 均さん(市教委職員)が博士号!~中世石造物の研究(平成23年12月19日掲載)
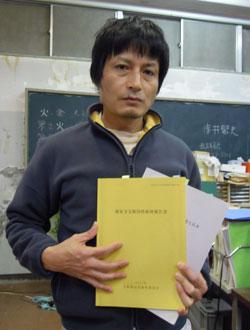
山川さん
山川さんは、平城京の十条大路遺構を発掘していた大和郡山市教委の職員です。筒井城跡の発掘調査説明や額安寺(額田部寺町)の石塔の解体修理の時にもお会いしました。
山川さんが、学位論文(大学院に提出した論文)が認められて博士号をとった、という日頃の地道な努力と熱意に感銘を受け、取材させていただきました。北小学校(北郡山町)敷地内の建物に山川さんの資料机がありました。
さっそくですが、論文の内容と評価された点は?(大変ぶしつけな質問で、すいません!)
― 中世石造物の研究です。中世を考える上で、石塔などの石造物は重要です。鎌倉時代の石塔が本市には非常に多いのです。 なぜだか分かりますか? (みなさんも、考えてください!)
そして、それらが中国から伝わってきた事が証明することができたのです。

額安寺 石塔 宝篋印塔
山川さんは普段は無口な男性ですが、研究に関しての質問には懇切丁寧に多くの事を話していただきました(…が、学術的で大変難しい!)。
近畿や関東を中心に1,000基以上の石造物を見て歩き、形状を記録し、銘文を読み、関連文献を調べたこと。また、中国の石造物を調べるために、中日の研究者に呼びかけて中国に何回も参加された経験から生まれた独自の説が、書かれた著書(写真1)や今回の論文(約700ページ)に結実されているようです。

額安寺 石塔 忍性五輪塔
山川さんの論文(要旨)を読まれた、市文化財審議会会長の長田光男先生から次の激励文が届きました。
山川さんの研究目的と内容理解に、大変役立つ資料になると思い、下記に参考文として、長田先生の了解を得て掲載させていただきます。
石造物の思想的意味や時代背景、また高僧の活動などが宝篋印塔(主に中世以降、供養塔や墓碑として建立された塔婆の一形式)から読み取ることができるんですね。
大和郡山市内に中世時代の石造物が多いのは本市で修行した忍性、叡尊(白土町で出生)などの高僧の思想、信仰の深さに大きな影響があるようです。
(資料写真は、教育委員会 生涯学習課 提供)
参考文
山川均氏の学位論文要旨を読んで ~大和郡山市文化財審議会会長 長田光男
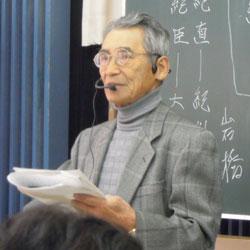
日頃からこつこつと発掘調査や石造物の研究に打ち込んでおられる山川氏の活動に対して、かねがねから敬愛を感じていたところです。
このたび、「中世石造物に関する歴史考古学的研究」をテーマとする学位論文が高く評価されて、みごと博士の称号を獲得された由、誠におめでとうございます。
以下、その要旨を読ませていただいて感じたことを次に述べてみます。浅学な私ですので、全くはずれた、的を射ていない箇所が多いかと思いますが、お許しください。
- 全体の流れを見て、日本における石造物、とくに宝篋印塔の定着していく経緯がよく分かる。
- それに関わった人物とその人の思想(宗教上の信仰も含めて)がよく分かる。
- 石造物の発達する時代背景も諸々に読み取ることができる。とくに、集村化の進む中での石造物造立ということが興味深い。集村化と信仰、そして石造物への傾斜…その辺りをもっと深く知りたい。
- 大和における石造物、とりわけ宝篋印塔の造立は忍性らを中心とする強力な活動家がいたからに違いないが、他地方においての石造物の発達は、どのような要素があってのことなのだろう。そのことについても知りたい。
- 忍性と叡尊について。2人の間には多少距離をおくところがあるが、貧民救済活動や文殊信仰などでは一致した行動をとっている。この論文上では叡尊の石造物に関わる活動があまり触れられていない。その辺りを知りたい。
- 大和各地に残る石造物…五輪塔、宝篋印塔、それに阿弥陀地蔵などの石造物を多く見かける。作者も伊派・大蔵派・橘派などの石工がいて数多く造り出している。それらは、どの工房で、どこで、そしてどこから採出の石材で造り出したのであろうか。それによっては、浄土教その他の宗派の普及のほども分かるのではないだろうか。
以上、拙い感想を列挙し申し訳ありません。
山川氏の今後の益々のご発展を祈る次第です。 以上









更新日:2021年03月19日