まちかどレポート260
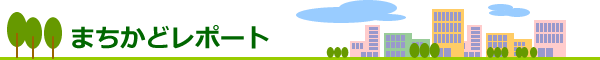
まちかどレポート260 郡山再発見ウォーク『初夏の矢田丘陵に饒速日命を訪ねて』報告
(まちかどレポーター 丸山)
郡山再発見ウォーク『初夏の矢田丘陵に饒速日命(ニギハヤヒノミコト)を訪ねて』報告(平成24年6月14日掲載)
6月2日(土曜日)、郡山再発見ウォークに行ってきました。この日のコースは次の通りです。
横山口バス停~一の矢塚~矢田坐久志玉比古神社~東明寺~三の矢塚~民俗博物館(解散)~矢田東山バス停(約6.5キロメートル・午前9時~13時)
この日はいつものレポートと違って、僕自身が市民の皆さんを案内するガイドとしてウォークに参加してきました。当日の参加総数は50名前後てす。
一の矢塚に向かう前、「参加された皆さん、今日一日は想像逞しくして、夢とロマンを実感しましょう!!」とアナウンスしました。そして、「今回は矢田丘陵の山麓を中心に、一の矢塚・矢田坐久志玉比古神社・東明寺・邪馬台国推定地・民俗博物館へ歩き、初夏の風情を楽しみましょう」とお話ししました。

民俗博物館での散策。6月2日、携帯で撮った唯一の写真です。
したがって、今回の本番レポート写真は一枚しかありません。本番の前、5月3日にコース下見をしました。そんな訳で、下見の時の写真を織り交ぜてこのレポートを見てください。
1.一の矢塚・二の矢塚・三の矢塚(邪馬台国伝承地)
矢田町には、小字の「一の矢」と称する地名と小さな塚があります。
伝説によると、櫛玉饒速日命(くしたまにぎはやひのみこと)が地上に降りて来た時、「天神より天の羽々矢、天の羽々弓賜わり祝いて、三本の矢を射放ちてその落ちし所に宮居せんと。すなわち、この矢田に落ちたり・・・」一の矢が落ちたのが、この塚の地。二の矢は矢田坐久志玉比古神社に、三の矢は同神社北方500メートルの地に落ちたと伝えられています。

横山口バス停から南5分のところにある、一の矢塚伝承地

三の矢塚(邪馬台国伝承地)

邪馬台国伝承地で、県外から来られた皆さんに簡単に説明しました。
2.矢田坐久志玉比古神社
櫛玉饒速日命(くしたまにぎはやひのみこと)と御炊屋姫命(みかしきやひめのみこと)を祭神とする延喜式内大社で、矢田郷の総鎮守。本殿は重要文化財(室町時代)として国の指定建造物です。
また、物部神話の「天磐船に乗りて大虚空(おおぞら)を翔行り(かけめぐり)・・・・」という古事により、飛行の祖神として「飛行機神社」の名で親しまれています。

矢田坐久志玉比古神社。
二の矢塚は拝殿を過ぎて左側にあります。
3.扁額・大日本飛行協会奉納のプロペラ
楼門のプロペラは中島飛行機製・陸軍九一式戦闘機です。昭和18年に大日本飛行協会大阪支部が奉納しました。このプロペラには堀丈夫陸軍中将より『神威赫奕』と揮毫。プロペラの上方には源田実の筆になる「航空祖神」と書かれた板碑も掲げられています。

大日本飛行協会奉納のプロペラ(本物ですよ)
4.東明寺
鍋蔵山と号し、高野山真言宗。本尊は薬師如来。松尾寺、金剛山寺とともに矢田丘陵の高所に建てられた歴史の古い山岳寺院の一つです。
矢田村の惣鎮守である矢田坐久志玉比古神社の神役を勤めていました。寺宝には、重要文化財の木造薬師如来坐像、木造地蔵菩薩坐像、木造毘沙門天立像、木造吉祥天立像があります。いずれも平安時代の作です。なお、裏山には本多家の跡目相続をめぐる争いである「九六騒動」で活躍した郡山藩家老・都筑惣左衛門の五輪塔があります。

新緑の美しい東明寺

東明寺の西、竹藪の中にある郡山藩家老都筑惣左衛門の五輪塔
5.奈良県立民俗博物館・大和民俗公園
1974年(昭和49年)に開館。「奈良に暮らす人々が、その風土の中で育み、改良工夫をかさねながら維持してきた生活用具など民具の数々約42,000点を収集し、これらを保存、展示公開する博物館」です。
大和民俗公園は、「26.6ヘクタールの広大な敷地を有し、自然との共生の場「里山」を活かしつつ「みんぱく梅林」「みんぱくしょうぶ園」があり、四季折々の草花、森林浴等を楽しむ」ことができます。「昔懐かしい江戸時代の民家15棟が「町屋」「国中(奈良盆地)」「宇陀・東山」「吉野」の4ブロックに分けて移築復原されており、自由に見学できます」。
しょうぶ園の開花状況は「これからが楽しみだ」というレベルでした。

さつきの美しいしょうぶ園









更新日:2021年03月19日