まちかどレポート299
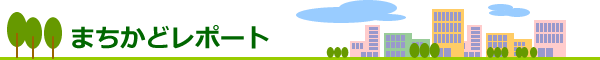
まちかどレポート299 旧臼井家住宅(県立民俗博物館)で新たな取り組みがスタートしました
(まちかどレポーター 丸山)
旧臼井家住宅(県立民俗博物館)で新たな取り組みがスタートしました(平成24年12月13日掲載)
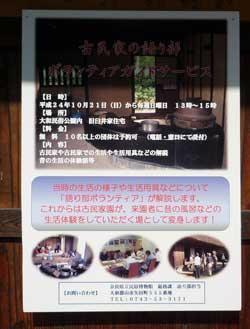
語り部ボランティアガイドサービス紹介のチラシ
矢田町にある県立民俗博物館で、10月21日~12月23日の間、毎週日曜日午後1~3時の間「語り部ボランティア」によるガイドサービスが試行的に始まりました。(本格的な運用は来年春3月の予定とのことです)


臼井家住宅の外観(左手は主屋、右手は内蔵)
解説場所は大和民俗公園内の国の重要文化財「旧臼井家住宅」で、当時の生活ぶりや生活道具などを解説。
このガイドサービスは、大和民俗公園内に移築復元されている古民家15棟の有効活用策として考案されたそうです。
語り部ボランティアガイドが、日曜日の午後1~3時に常駐し、訪れた人に解説します。10人以上の団体であれば、この時間以外でも事前予約でガイドサービスを行うとの事でした。

語り部ボランティアの杉本さん。
今日は語り部ボランティアガイドとしてデビューの日だったそうです。
なお、民俗博物館では、古民家の「かまど」などを使ったイベントも計画されており、『展示見学のみだった古民家を「昔の風習」などを体験してもらう場に変えていきたい』としています。

昔懐かしいかまどですね。
臼井家の概略
旧臼井家住宅はもと高市郡高取町上土佐に所在していた町家です。建物の構造手法上は18世紀前期頃の建築と推定されています。高取町上土佐(旧土佐町)は、植村藩2万5千石の城下町で、町奉行支配下の半商半農的な町でした。臼井家は伊勢から当地に移り、旧高取城大手へ通じる道の北側に屋敷を構え、代々、屋号は「伊勢屋」。藩の公用伝馬の役を務め、酒、醤油の販売を営む他、大年寄を務めたと伝えられています。
建物の構造
主屋は間口約9間、奥行3間半、切妻造の萱葺で、表裏側に庇を付け、本瓦で葺かれています。正面向って右手に「土間」をとり、表隅に商いの場所とした中二階付きの「下店」を設け、その裏は釜屋となっています。
来年春からの本格運用が期待されます。ぜひ、訪れたいですね。

主屋は間口約9間、奥行3間半、切妻造の萱葺で、表裏側に庇を付け、本瓦葺です。

主屋から内蔵を望む。 来年春からの本格運用が期待されます。ぜひ、訪れたいですね。


12月1日から2月3日までは、企画展「大和の昔の暮らし-衣・食・住-)が開催されています。

企画展の展示物









更新日:2021年03月19日