まちかどレポート119
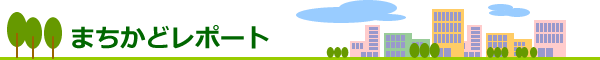
まちかどレポート119 「関西文化の日」の民俗博物館
(まちかどレポーター ジル)
「関西文化の日」の民俗博物館(平成22年12月7日掲載)
「関西文化の日」とは、関西一円の文化施設で関西文化をもっと知ってもらうために、11月の一定期間の入館料を無料で利用できる日の事です。関西一円の約400施設、奈良県は36施設です。
2003年3月河合隼雄文化庁長官(当時)が「日本の社会を文化で元気にしよう」 「そのためにはまず関西からはじめましょう」という「関西元気文化圏構想」を発表し、これに応え同年8月に関西の自治体、経済界、関係事業者、報道関係などの代表者が集まり発足したものです。
矢田町の奈良県立民俗博物館は、11月13日と14日が実施日だったので行って来ました。
博物館の常設展「大和のくらし」は知っておられると思いますが、企画展「日々のくらし―子育ての民俗―」と、関西文化の日記念ワークショップ「はたおりから大和を語る」がありました。
企画展「日々のくらし―子育ての民俗―」は、奈良県内に伝えられて来た、明治・大正・昭和の子育てにまつわる風習が取り上げられていました。「地域の中の子ども」 「無事を願って」「誕生と成長」の構成で、子宝、安産、子育てにまつわる小絵馬、まじないやお守りなど、誕生から七五三に至るまでの日々の用具と節目ごとに行われる行事などが展示紹介されていました。
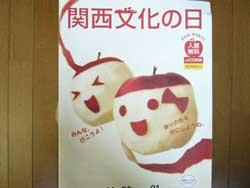


「ジョウトンバ」 「氏子入り絵馬」
中和地域を中心とし初宮まいりの際、氏子のしるしとして絵馬を奉納する風習があった。
その年に氏子入りした子どもが連名で大絵馬を奉納する事もあった。

「無事を願って」
子育て祈願の小絵馬

「子宝・安産願い」
今日ほど科学的な方法が発達していなかった時代、神仏に祈る事、見守る家族や周囲の人の願いですこやかに育つようにと地域社会で子どもを支えていた。

「七五三」
七五三を一つの区切りとして幼年期を脱し、子どもの仲間への加入社会との主体的な関わりが始まる。

子守り箱と子守りイゴ
子守りふごとボテコ(オシメ入れ)

ちまき作りの枡とひし餅の型
初節句の時娘の嫁ぎ先に大型のちまき2個を届ける風習があった。嫁ぎ先の家格に応じて五合、四合、三合の枡を使いわけた。(左に半分写っている大椀に入れて持って行った。)
記念ワークショップ「はたおりから大和を語る」は、奈良市月ヶ瀬を拠点に奈良晒の紡織技術の保存・伝承活動を続けられている、月ヶ瀬奈良晒保存会による実演・実習を交えて作業工程と特色について説明がありました。たくさんの人達が熱心に聞かれ体験されていました。

大和機(やまとばた)


かつて大和は、全国に知られた一大織物産地でした。奈良晒、大和木綿など、近世~近代のくらしを支えた、はたおりの伝承技術と用具から、郷土の知られざる歴史と文化について学ぶ事ができました。









更新日:2021年03月19日