まちかどレポート397
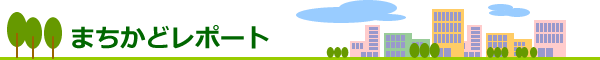
まちかどレポート397 お正月の農作業~植槻八幡神社のオンダ~
(まちかどレポーター 後藤)
お正月の農作業~植槻八幡神社のオンダ~(平成27年1月14日掲載)
1月7日、郡山城跡の北に鎮座する植槻(うえつき)八幡神社にてお田植え行事が行われました。
お田植え行事は「オンダ(御田)」とも言い、豊作を祈願する神事です。
所作(しょさ)役の方々による苗代作りや、田植えの農作業が模倣されます。
午前10時すぎ、かつてのお米作りでは大切な働き手であった牛が準備を整え、神前へ向かいました。


神事を前に一同、宮司さんからお祓いを受けています。
よいお米を作るには、よい土づくりが肝心。
先人はその作業工程に合わせ工夫を凝らした農具を開発し、改良を重ねました。
さあ、農作業の始まりです。

唐鋤(からすき)と呼ばれる農具で田の土を掘り起こします。
その作業は重労働がゆえ、かつては牛の力を借りて作業をしていました。
次は馬鍬(まんが)掻きです。
耕した土を平らにしています。

土づくりが完了したら籾撒きをし、いよいよ田植えを迎えます。
苗に見立てた松苗で田植えの所作を模倣しています。


皆さん、笑顔で田植えを見守っているのが分るでしょうか?
田主役の方が時折、即興の面白いセリフを言っているのです。朝の冷たい空気が立ち込める境内が一瞬、あったかい雰囲気に包まれました。
おぜんざいの接待を受けている間に、境内ではみかん撒きが始まっていました。
黄色いみかんが宙を舞い、皆さん、この時ばかりは童心に帰ったようです。

大和郡山市内では、植槻八幡神社の他に小泉神社等でもオンダが行われています。
帰り際、神事に使用された農具が境内に置かれていたのでよく見ると、鍬には天保10年の墨書銘が。


この当時は、牛もまだまだ現役真っ盛りで活躍していた時代。
作物の出来は、生活を大きく左右していたことでしょう。
豊作を願う村人の願いは、宙を舞って輝いていたみかんのように今以上に大きな大きなものだったでしょう。









更新日:2021年03月19日