まちかどレポート76
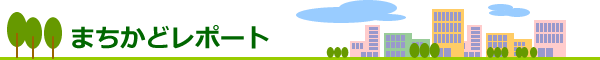
まちかどレポート076 矢田は古代信仰の聖地!
(まちかどレポーター フリータ・K)
矢田は古代信仰の聖地!(平成22年8月27日掲載)
矢田丘陵の東斜面は開かれた古代信仰の聖地。
猛暑のなか、汗をぬぐいながら、矢田の伝承遺跡を訪ねてみました。
矢田坐久志玉比古(やたにいますくしたまひこ)神社(写真1・本殿は室町時代、八幡神社は鎌倉時代、どちらも国重要文化財。矢田小学校の西側にあります。)は、饒速日命(にぎはやひのみこと)が天磐船(あまのいわふね)に乗って降臨した時に三本の矢を射て落ちた所を住居にしたと伝え、この付近に一の矢塚、二の矢塚、三の矢塚が伝えられています。

写真1
一の矢塚は一番南にあります(写真2)。
ここは、草が伸びていれば見つけにくい処です。

写真2
二の矢塚(写真3)境内にあります。

写真3
当神社は、桜門やプロペラが奉納され、航空祖神として信仰(矢落(やおち)大明神とも呼びます)されています。(写真4)

写真4
北村集落に向かう途中に、三の矢塚・邪馬台国伝承地を示す碑(写真5)が建っています。(大阪教育大学名誉教授 鳥越憲三郎氏の論説に基づいて、大和郡山市観光協会がここに建立したもので、説明板があります。)


写真5
『旧事(くじ)本紀』に、この三本の矢を放ったこの地が物部(もののべ)一族の本拠地であるとし、邪馬台国はこの物部氏のつくった部族国家で、女王卑弥呼が君臨した地であるとしています。
考古学上、説はいろいろありますが、地元ではこの地を「宮処(みやどこ)」と呼んでいます。
(参考資料、「続・奈良点描」・「山里・古社寺探訪」(どちらも長田光男著)。市立図書館の郷土資料のコーナーにあります。写真は7月23日に撮影。)









更新日:2021年03月19日