国民健康保険の給付
目次
- 療養の給付
- 高額療養費
- 70歳未満の人の高額療養費自己負担限度額
- 70歳以上75歳未満の人の高額療養費自己負担限度額
- 高額療養費の申請手続きなど
- 厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
- 高額療養費の現物給付
- 高額介護合算療養費
- 入院費の食事代
- 療養費の支給
- その他の給付
- 訪問看護療養費
- 出産育児一時金の支給
- 葬祭費の支給
- 移送費の支給
- 一部負担金の徴収猶予及び減免
1.療養の給付
病気やけがをしたとき、病院などの窓口でマイナ保険証等を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険から支払われます。
医療費の自己負担割合は次のようになります。
| 義務教育(小学校)就学前(注釈1) | 2割 |
|---|---|
| 義務教育(小学校)就学後、70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満(注釈2)で現役並み所得者 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満(注釈2)で一般、低所得者1・2 | 2割 |
(注釈1)6歳に達する日以降の最初の3月31日(誕生日が4月1日の人は、その前日の3月31日)まで
(注釈2)70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで
70歳以上の人の医療費
75歳になるまでは国民健康保険で医療を受けます。自己負担割合を印字した資格情報のお知らせまたは資格確認書を交付しますので、病院の窓口などで提示してください。75歳からは国民健康保険をぬけて後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
2.高額療養費
1ヵ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額を超えたときは申請により、超えた額の払い戻しを受けることができます。自己負担の限度額は、70歳未満の人の場合と70歳以上75歳未満の人の場合で異なります。
70歳未満の人の高額療養費自己負担限度額(世帯単位)
| 区分 | 所得要件 | 限度額 |
|---|---|---|
| 上位所得 ア | 基礎控除後の総所得金額が901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【4回目~140,100円】 |
| 上位所得 イ | 基礎控除後の総所得金額が600万円~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【4回目~93,000円】 |
| 一般 ウ | 基礎控除後の総所得金額が210万円~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【4回目~44,400円】 |
| 一般 エ | 基礎控除後の総所得金額が210万円以下 | 57,600円【4回目~44,400円】 |
| 非課税 オ | 住民税非課税 | 35,400円【4回目~24,600円】 |
【 】内は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
高額療養費計算上の注意
- 同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算です。
- ひとつの医療機関ごとに計算(医療機関が違う場合は別計算)。
- ひとつの医療機関でも、外来と入院は別計算。
- 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代などは高額療養費の対象外です。
- ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
70歳以上75歳未満の人の高額療養費自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 【現役並み所得者3】 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈) |
| 【現役並み所得者2】 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈) |
| 【現役並み所得者1】 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈) |
| 一般 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(注釈) |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈)過去12ヵ月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は下記の通り
| 所得区分 | 外来+入院(世帯単位) 【4回目以降の限度額】 |
|---|---|
| 【現役並み所得者3】 課税所得690万円以上 |
140,100円 |
| 【現役並み所得者2】 課税所得380万円以上 |
93,000円 |
| 【現役並み所得者1】 課税所得145万円以上 |
44,400円 |
| 一般 | 44,400円 |
- 現役並み所得者とは、70歳以上の人で、課税所得145万円以上の人が同一世帯にいる人。ただし、70歳以上の人の収入の合計が一定額未満(単身世帯で年収383万円未満、2人以上の世帯で520万円未満)の場合、申請により「一般」となります。また、70歳以上の大和郡山市国民健康保険被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円以下である場合も「一般」となります。
- 70歳以上の人で、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で、低所得者I以外の人。
- 70歳以上の人で、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算。給与所得から10万円を控除。)を差し引いたときに0円となる人。
高額療養費計算上の注意
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算。
- 病院、診療所、歯科、調剤薬局の区別なく合算して計算。
- 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代などは高額療養費の対象外です。
- 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
高額療養費の申請手続きなど
- 高額療養費の支給申請ができる可能性のある方に「高額療養費支給申請書」を送付しています。
- 医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)と照合して支払い手続きをするため、申請書の送付は診療を受けた月から早くとも3ヵ月後になります。レセプトの到着が遅れた場合は申請書の送付時期も遅れます。申請書を受付した月の翌月末を目途に支給します。該当していると思われる方で、申請書が届かない場合は、お問い合わせください。
- 申請できる期間は、原則、診療を受けた翌月から2年です。
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」(窓口への申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、その診療にかかる毎月の自己負担額は、10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全の人で、70歳未満の区分ア・イの人は20,000円)になります。
高額療養費の現物給付
高額療養費については、医療機関窓口(外来・入院)での負担が自己負担限度額までとする現物給付の取扱いができます。マイナ保険証を利用しておらず現物給付を受けたい人は、自己負担限度額などを記載した認定証が必要となります。事前に窓口へ申請してください。認定証は、年齢、所得区分に応じて次のとおりです。(保険税を滞納していると交付されません。)
| 年齢 | 世帯区分 | 認定証 |
|---|---|---|
| 70歳未満 | 住民税非課税世帯以外 | 限度額適用認定証 |
| 70歳未満 | 住民税非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
| 70歳以上75歳未満 | 現役並み所得者2・1 | 限度額適用認定証 |
| 70歳以上75歳未満 | 低所得者2・1 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳以上75歳未満の現役並み所得者3及び一般の所得区分に該当する人は、資格確認書により現物給付の取扱いができますので、認定証は必要ありません。
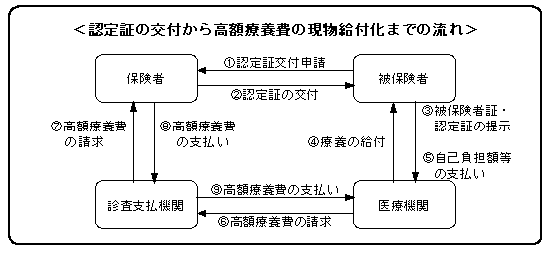
高額介護合算療養費
毎年8月から翌年7月までの1年間に国民健康保険と介護保険の両方で負担した自己負担額の合計が高額になったときに、次の自己負担限度額が適用されます。
70歳未満の人(国民健康保険+介護保険)
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 上位所得 ア | 212万円 |
| 上位所得 イ | 141万円 |
| 一般 ウ | 67万円 |
| 一般 エ | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 オ | 34万円 |
所得区分については、高額療養費自己負担限度額の区分を参照してください。
70~74歳の人(国民健康保険+介護保険)
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
|---|---|
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
141万円 |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 |
所得区分については、高額療養費自己負担限度額の区分を参照してください。
3.入院時の食事代
入院したときの食事代は、標準負担額だけを負担し、残りは国民健康保険が負担します。
食事代の標準負担額(1食あたり)
| 区分 | 負担額 |
|---|---|
| 一般(下記以外の人) | 510円(注釈1) |
| 住民税非課税世帯 低所得者2 (90日までの入院) |
240円 |
| 住民税非課税世帯 低所得者2 (過去12ヵ月で90日を超える入院) |
190円 |
| 低所得者1 | 110円 |
(注釈1)難病患者等は、300円です。
(注釈2)標準負担額の減額は、住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」、70歳以上75歳未満で低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。入院する前に窓口に申請してください。
65歳以上75歳未満の人が療養病床に入院したときの食費と居住費の標準負担額
| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円 | 370円 |
| 低所得者2 | 240円 | 370円 |
| 低所得者1 | 140円 | 370円 |
入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊椎損傷、難病等)が継続する患者は、食材料費相当額のみの負担となります。
4.療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた7割~8割が支給されます。
- 急病などで、やむを得ずマイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
- 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に負傷したり、疾病にかかり治療を受けたとき
上記のぞれぞれの場合により、申請に必要なものが異なります。
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで3ヵ月ほどかかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
5.その他の給付
訪問看護療養費
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに、申請により支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、異常分娩でも支給されます。
出産育児一時金は、原則として加入している健康保険から医療機関などに直接支払われ、出産費用から差し引かれます(直接支払制度)。
手続きとして、世帯主が出産予定の医療機関などで、申請・受取にかかる代理契約を直接交わしてください。
直接支払制度を利用しない場合は、国民健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。その場合は、いったん医療機関などに出産費用を支払うとともに、直接支払制度を利用しなかった同意書を国民健康保険の窓口にお持ちください。
- ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
申請に必要なものは、保険証、会葬礼状または葬儀費用に関する領収書(喪主の氏名の記載があるもの)です。
- 葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
移送費の支給
病気やけがのため移動が困難な人が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して国民健康保険が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
申請に必要なものは、マイナ保険証等、印鑑、医師の意見書、領収書(移送期間、距離、方法のわかるもの)です。
- 移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
一部負担金の徴収猶予及び減免
災害や特別な事情により生活が一時的に苦しくなり、医療費(入院の場合)の支払が困難になった世帯に対し、申請により、病院の窓口での支払い(一部負担金)を一定期間、徴収猶予または減免することができます。
申請には、世帯の収入、資産状況等必要な書類の提出、また調査を要しますので、事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2025年05月29日